これから、
おしゃべりの時代が来るので
おしゃべりで
お互いを豊かにしちゃう、
そんな
コミュニケーションを描いた
本を書きました。
本のタイトルは
『認識の交歓というアレ:
これからのコミュニケーション論』。
⤵︎
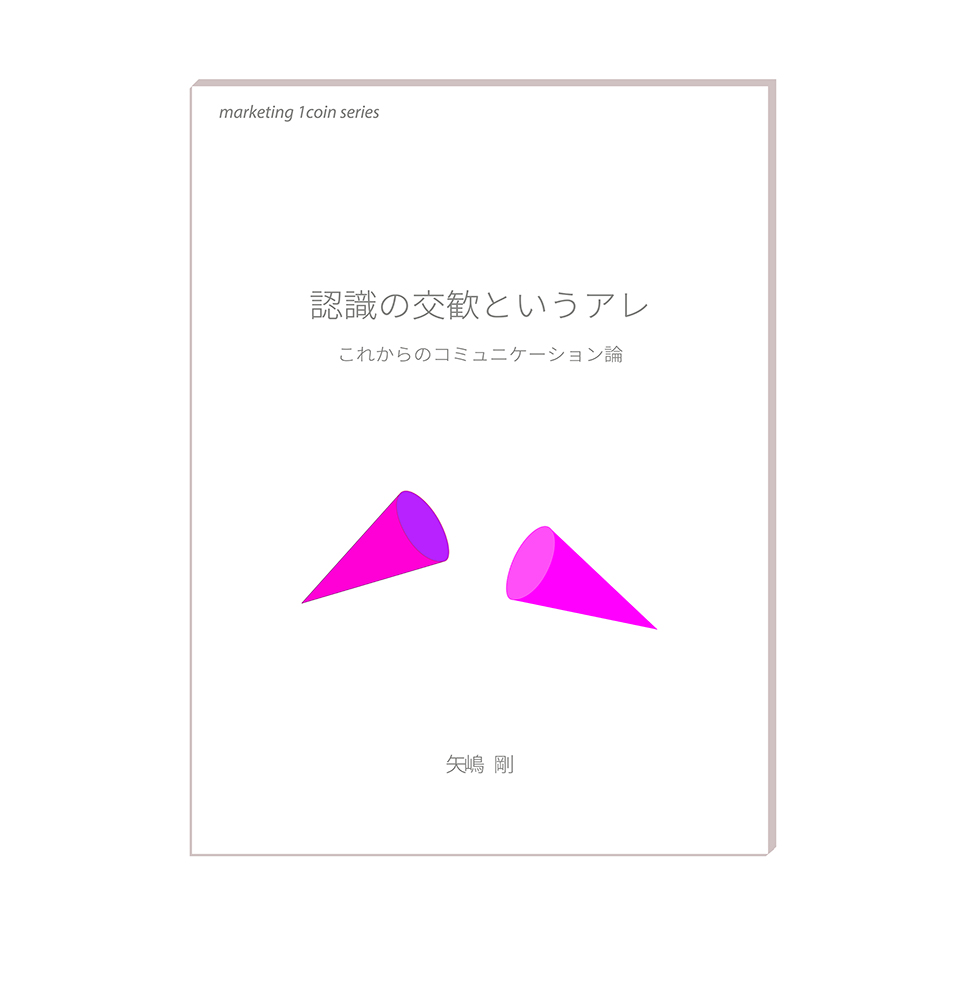
この本には、おしゃべりが
たくさん載っています。
Aさん「☆*△〒」
Bさん「%$◯@」 な
おしゃべりの数々が
登場します。
「どこか旅行に行きたいよね〜」
「南の島っていいよね〜」
「国内だと、やっぱり沖縄かな」(認識A)
「万座ってきれいだよね」(同B)
「近くに真栄田岬があって、
そこもきれい」(同C)
(以下省略。本書29ページより引用)
こんな調子で、
お互いの認識(:物事のとらえかた)が
楽しく交換(=交歓)されていく。
そして、人生が豊かになっていく。
そんなコミュニケーションを
どんどんご紹介していきます。
ですから、楽しい。
「あら、おもしろそう」
「こんなおしゃべりしたいなぁ」
になっちゃってください。
そして、ちょっと考えてください。
わたしたちの望むコミュニケーション
が、この本に書いてある「認識の交歓」
になっていくとき、どんな世の中になるんでしょう。
おしゃべりの時代が
来るのではないでしょうか。
声の大きい人(=有名人やインフルエン
サーたち)がしゃべりまくる、ああいう
おしゃべりじゃなくて、お互いの言うこ
とに耳を傾ける、話すほどにお互いを
高め合うおしゃべりが花開く世の中に
なるのではないでしょうか。
「カレーはまず玉ねぎを炒めて」
「ウチでは肉をまず炒めるよ」
「カレーには福神漬けを」
「ウチは紅生姜なの」
カレーライスの作り方を巡って、楽しく
おしゃべり。そして、もっとおいしい
カレーライスの作り方や食べ方が
その場で生まれちゃったりして。
テレビ→芸能人→SNS→インフルエン
サーと、話題を振りまくメディアや人が
次々と現れましたが、そんな情報攻勢に
みんな飽き飽きし、避けるようになり、
もっぱら、おしゃべり。おしゃべりの
ほうが遥かに豊か。それが常識な時代に
なると思います。そうなると…、
わたしたちと企業のコミュニケーション
って、どうなるんだろう。マーケティン
グ・コミュニケーションは、この先、
どうすべきなんだろう。
そんなこと、想ってみてください。
考えるべき深刻な問題は
「一方的」だと思います。
テレビは一方的。
SNSも次第に一方的に。
(どういうことかはブログで→)
(この本の中では「一方的に強いると
ーかるく広告批評ー」で触れています。
本書49ページ)
でも、わたしたちのしたいのは、
認識の交歓。
このギャップを放置し続けると…。
その分、新しいチャンスも
生まれていて…。
そんなアレコレが載っている
コミュニケーションの本です。とはいえ
話がマーケティングに囚われている
わけではなく。コミュニケーションと
いう行為がメインテーマ。
ですから、この本は、
コミュニケーション論の本として
お読みいただけます。
その証拠に、学問の各分野で
コミュニケーションがどう扱われて
きた?なんて話も書いてあります。
(「とりあえず、コミュニケーション論の
地図」をお読みください。本書4ページ)
言語学の権威、F.ソシュールさんは
コミュニケーションについて、
いったい何を指摘したのか。
そういう事も書いてあります。
この辺りも、この本で
バッチリになってください。
Apple Books と
Google Play ブックスで
購入いただけます。
Apple Books
Google Play ブックス
(試し読みも、できます)
P.S.
マーケティング・コミュニケーショ
ン、これからどうするんでしょう?
わたしたちは認識の交歓を求めます。
ですから、おしゃべりを楽しみます。
この流れに企業は付いていけるで
しょうか。今まで通り「一方的」に
すがり続けるのでしょうか。
とても気になっています。
そんなアレコレも含め、ご質問、
ご感想などありましたら
お気軽にお送りください。→
著者が返信いたします。