観察調査の簡単ガイドブック
『観察調査のすすめ』を
ご案内します。
こんな本です。⤵︎
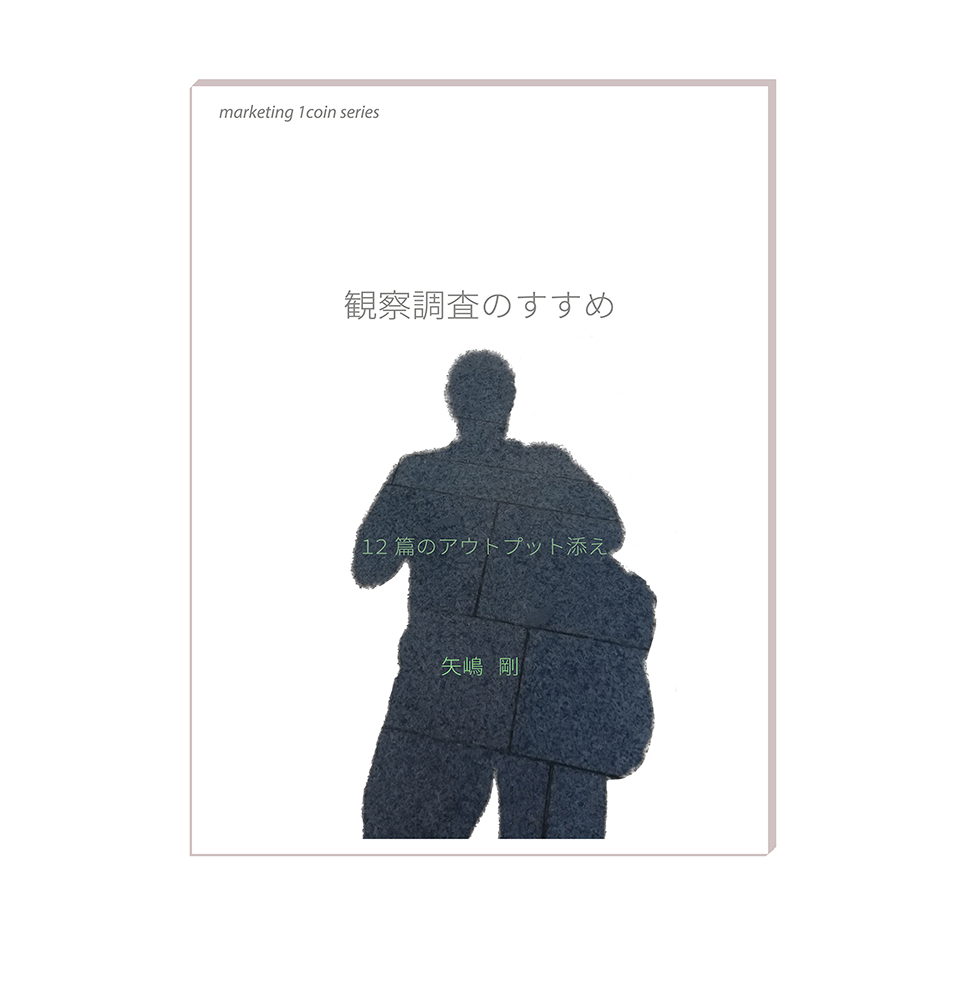
この本は
観察調査をおすすめしています。
観察調査してみて!って
訴えています。
なぜかと言うと
世の中が見えてくるからです。
百聞は一見に如かず。
事実は小説より奇なり。
自分の知る検索語の範囲でネット
検索し、検索順位上位のページを
読み、AIに補足質問し
「世の中、こうなっている」と
ミスリードしないために、
観察調査をして欲しいのです。
さて、その観察調査ですが、
とても簡単です。
現場に行って、人々を眺めるだけ。
ただそれだけで、いろんな事実が
分かってきます。
たとえば、映画館に行くだけで…⤵︎
今一番映画を観る人は、お爺さんです。(中略)館内での鑑賞態度も映画ファンの王道を地で行く感じです。二本立ての両館です。続けて観ると(注:ほとんどの人がそうします)、上映時間は三時間を超します。しかし途中トイレに立つ人はいません。頻尿に悩む年頃ですが鑑賞を妨げない水分コントロールは完璧です。バックの中のペットボトルをちびちび飲みます。空腹対策もばっちり。バックの中にはラップで包んだおにぎりやサンドウィッチが用意してあるのです。ですから正午を迎えると館内は突然のお弁当タイム。あちらこちらから…(以下省略)
が分かっちゃいます。
こういう効果を知っていただきたいので
著者は、この本に自身のおこなってきた
観察調査の結果を簡潔なエピソードに
まとめて書き下ろしました。今、引用し
た映画館の話は「永遠の映画ボーイズ」
のタイトルで登場します。そのページを
ご覧ください。⤵︎
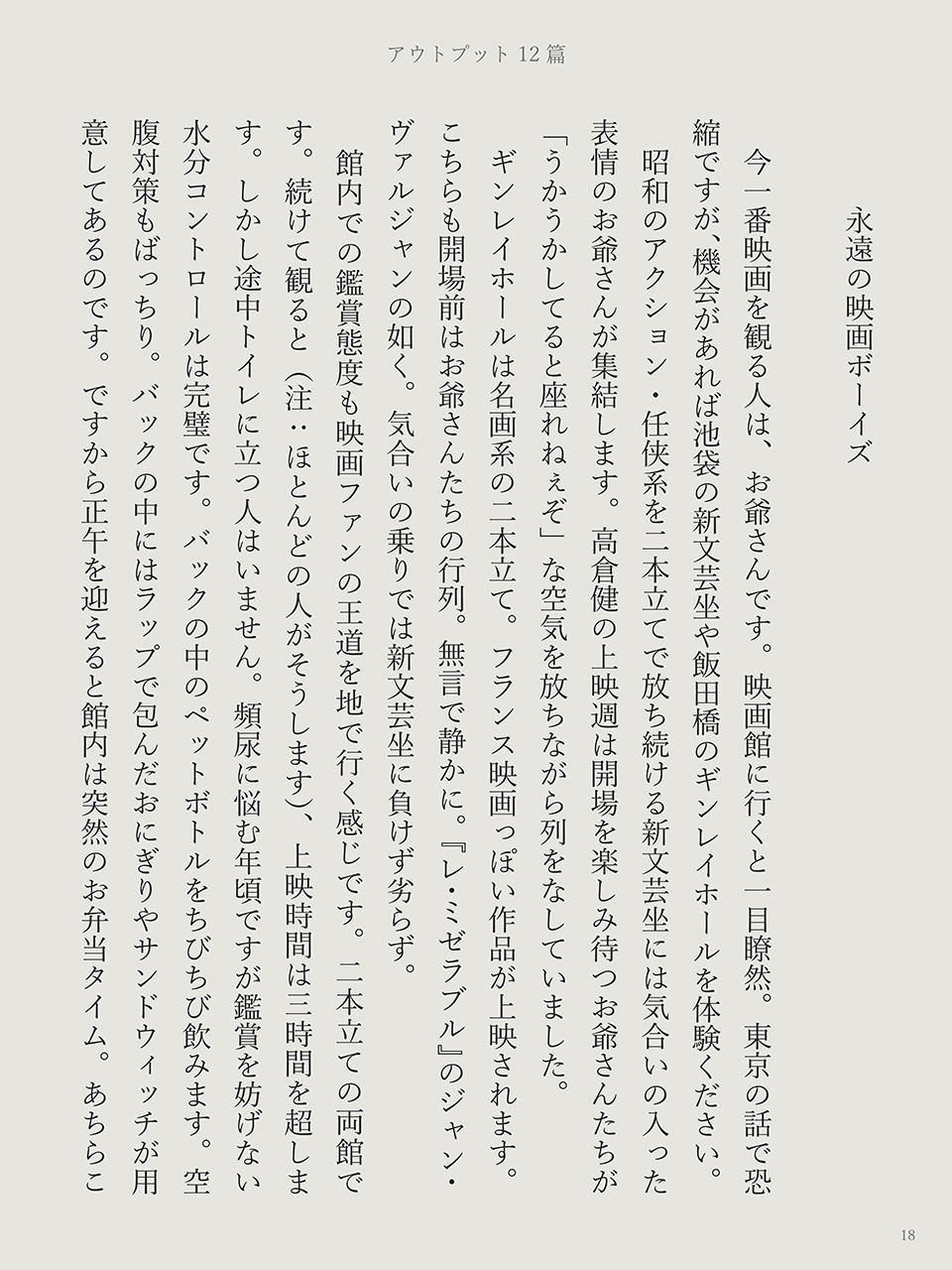
文庫本のエッセイみたいですよね。
こんな観察エピソードがこの本には
12本載っています。観察の舞台は、
映画館のほか、Bar、カフェ、
電車の社内、立ち食い蕎麦屋さん、
河川敷の野球場など。観察調査って、
どこでも出来るし、眺めるだけで
ほんとうにいろいろな事実が分かる
ということを知っていただければ!と
願っています。この本のサブタイトル
「12篇のアウトプット添え」には
そんな願いが込められています。
「ううーん、観察って」
「眺めるだけで、なるほどなぁ」
と思っていだければ幸いです。
調査のプロの人にも響くと思います。
「アンケート調査をするとなると、
お金も時間もかかるし、その割に
微細なことは分からなかったり
するし…」
「インタビュー調査は回答者の
ナマの言葉は聞けるんだけど、
その言葉を発する源となった現場の
様子が見えないんだよねー」
なんて落とし穴(=克服すれば成長)に
気づいていただけると思います。
「じゃぁ、やってみようかな!」
と思ったら、始めてください。
気になる場所で、時間のあるときに。
店に来るお客様を眺める。ライバル店の
お客様を眺める。話題の人気スポットに
いる人を眺める。ちらっと眺めるだけで
いろんなことが分かります。
「でも観察調査なんて初めてだし、
何をどうすればいいの?」
「観察調査を始めるには?」
で迷われたら、本の後半に載っている
「お試し時の注意事項」をお読みくださ
い。調査の仕方(=観察の仕方)や調査
結果のまとめ方が、わかりやすく書いて
あります。「社会調査とは?」な能書や
ウンチクが「まず眺める」「事実を身を
もって知る」バリア(=調査あるある)
にならないように書かれています。
さて著者(=わたし)ですが、今も観察
調査を続けています。20代から始めて
30年以上(=年齢がバレますねw)。
であらためて思うのは「観察調査って、
スゴいなぁ」ってこと。
ネットに◯◯と書いてあったけど、
テレビで△△と言ってたけど、
わたしが観察した事実は違うんだよね。
そういう事実に出会うことができます。
そういう事実が自分に独自の視点を
与えてくれます。
すると未来予想や政策立案の能力も
自然にアップしていきます。
ライフスタイルの未来を描いた
『新酒の季節は杉玉色に』の解説篇
「これからの消費論」は観察調査で
知った事実をベースにしています。
これからの地域振興の具体策を描いた
『地域発展の原理と8つのプラン』
のプラン(「なんだかとってもインド
な地域」ほか)も観察調査の成果を
その基礎に置いています。
ということで、やるほどに世の中が見え
てくる観察調査、顧客調査や消費者調査
にも使える観察調査、未来予想や政策立
案にも役立つ観察調査をご紹介させてい
ただきました。
観察調査、おすすめです。
『観察調査のすすめ』、
ご一読ください。
Apple Books と
Google Play ブックスで
ご購入いただけます。⤵︎
Apple Books
Google Play ブックス
(試し読みできます)
P.S.
観察調査は英語で observation survey
または observational methodsと言います。
社会の実態を調べる社会調査の手法として
認められているので正式な呼称があります。
→ wikipedia
P.S.2
「人の観察は再現不可=科学的な検証は
無理=信用できない」な研究者特有の
感性を理由に観察調査を軽視する大学の
先生がいます。 こういう話です→ブログ
一方で認める先生もいます。要は先生た
ちの好き嫌いであり、観察調査の価値は
揺らぎません。世の中の実態を知る方法
として観察調査は有効で優秀なのです。
(cf.ドキュメンタリー)
P.S.3
観察調査を集中力を持って続けると、
その人の観察眼が鋭くなります。
Aさんが見落とした事実をBさんは
見逃さなくなるのです。観察眼の鋭い
人は鈍い人よりも優れた調査をします。
そして役に立つレポートを書きます。
そんな彼らを有するとすばらしい調査
結果を手にすることができます。
(→知見メモ「消費者調査は人次第」)